伝統工芸の後継者不足を解決する方法について考える
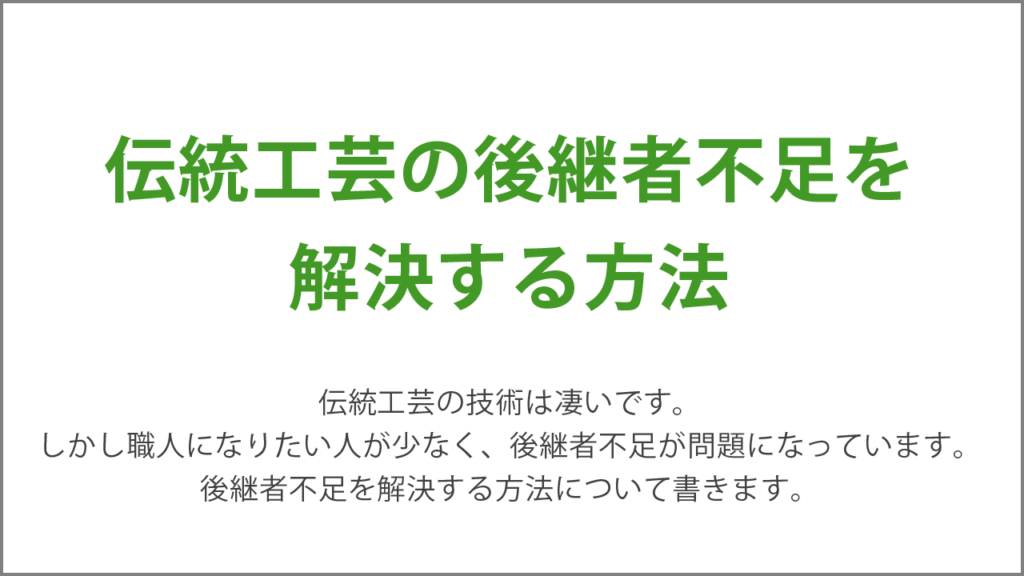
私は伝統工芸の技術は凄いと感じています。TVで職人の技を見ても、凄いと感じますし、自分自身も日常的に伝統工芸品を使っています。
また個人的に支援している経営者からも、伝統工芸の魅力や後継者不足の話が出てきます。その都度、伝統工芸をどうやって広めるか、後継者不足をどうするか考えています。
この記事では今まで私が考えてきたことをまとめてみます。実行に移すまでにはまだ至らないのですが、情報収集したことはまとめています。
伝統工芸の後継者不足に悩む方や、伝統工芸に興味がある方、伝統工芸の作り手になりたい方の参考になれば幸いです。
伝統工芸の後継者不足について
後継者不足の現状
あなたも伝統工芸の後継者不足の話を聞いたことがあるかもしれません。
どのくらいか気になったので総務省の資料を読んでみました。こちらのPDFの25ページ目に生産量と従業員数のグラフがあります。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000818483.pdf
このグラフでは1998年から2016年までを対象としています。
なんと従業員数は11万5千人から5万8千人へと半減しています。生産額も2,784億円から927億円へと約3分の1まで減っています。
従業員数が約半分、売上が約3分の1では、従業員の給与水準もよほど効率化していなければ、単純計算で3分の2くらいに減っている可能性があります。
職人になりたい人が少ない
これだけ伝統工芸の従業員数が減っているということは、伝統工芸の職人になりたい人がいないということを表しています。
たしかに人気がある業種を見れば、商社やコンサル、金融、メーカーなどでしょう。そして最近はITも人気があります。伝統工芸が人気の業種に挙がってくるのを見たことがないです。
伝統工芸品を作っている会社は地場中小企業が多いため、認知度も給与水準も低いからでしょう。
後継者不足を解消する方法
まずは私が考えたり調べたりした後継者不足を解消する方法について書いていきます。
職人養成学校を設立する
伝統工芸の職人が少ないなら育成すればいいという考えがまず出てきます。
学生にせよ転職を考えている社会人にせよ、仕事を探す前にまずは技術を学べる学校が必要です。
そこで伝統工芸の技術を学べる学校を作ればいいという発想が出てきます。
マッチングの仕組みを作る
伝統工芸に興味がある人と、伝統工芸の会社をマッチングさせる仕組みを作るという方法もあります。
例えばマッチングサービスとしてのWebサイトです。他には国や自治体、あるいは伝統工芸を扱う商社か伝統工芸の組合がマッチングイベントを開催するなどです。
伝統工芸の美しさや技術の凄さをアピールすることで、伝統工芸に興味がある人にやってみようかなと思わせるのです。
M&Aを活用する
私が一番現実的で確実かもしれないと考えている方法がM&Aです。
今やM&Aは後継者不足に悩む多くの企業にとって、後継者探しの選択肢の1つとなっています。
そこで後継者に悩む伝統工芸の会社派、次のような候補者への売却を検討します。
- 経営者が一回り若い同業他社
- 独立して伝統工芸に取り組みたい人
- 伝統工芸に魅力を感じている商社
- 伝統工芸の存続を目指してM&Aを行っている会社
Local Localという会社があります。この会社は後継者不足の酒蔵をM&Aして総合酒類ホールディングスを目指しています。
酒蔵も日本の伝統産業の1つです。このようにホールディングス化を目指して後継者不足の会社をM&Aしている会社に引き継いでもらうという方法もあります。
何より規模を大きくできれば資金力もできて、給与水準も挙げられます。会社の規模は給与水準に大きな影響を与えます。
日本に興味がある海外の方に引き継いでもらう
Youは何しに日本へ?という番組があります。
https://www.tv-tokyo.co.jp/youhananishini
この番組にはたまに伝統工芸を学びたいという方が登場します。
私が支援している経営者の中に、伝統工芸に興味がある経営者がいます。この人と話していてよく話題に出ることが、伝統工芸は海外の方に高い価値で買ってもらえるということです。
日本の伝統文化に興味がある人は世界中に沢山います。だから伝統工芸も海外に売るといいと私は考えています。
そこで日本の伝統文化や伝統工芸に興味を持った海外の方に後継者になってもらうのも1つの方法だと私は考えます。
東洋経済によく記事を書いているデービッド・アトキンソンという人がいます。
デービッド・アトキンソン | 著者ページ | 東洋経済オンライン | 社会をよくする経済ニュース
この人はイギリス人ですが、大学で日本学を学び、就職してからはずっとゴールドマンサックスの日本支社に勤めていたそうです。
そして日本の伝統文化にも興味があり、神社の修復を行う会社の後継者になっています。
日本人があまり伝統工芸をやりたくないなら、日本の伝統文化や伝統工芸に興味がある海外の方に後継者になってもらうのもありでしょう。
プロデュースに力を入れる
私が一番重要と考えていることがプロデュースです、
伝統工芸の職人の技術は素晴らしいです。しかしいくらいいものを作っても、伝える活動と売る活動がなければ売れませんし、ユーザーに使ってもらうことはできません。
だから職人が作った素晴らしいものを素晴らしいとちゃんと伝える活動を行う必要があるのです。そして世界中の多くの人の目につくようにするのです。
ここではマーケティングはもちろんですが、デザインやブランディングの考え方も重要になります。
伝統工芸のプロデュースで特に重要になるのはブランディングデザインだと私は考えています。
ブランディングデザインはデザインの力を活用してブランディングを行う活動であり、経営戦略にも大きく関わってきます。
いいものを作って、いいものだと伝えて、そして買ってもらうという流れを作るのがブランディングデザインです。
伝統工芸では既にいいものは作れています。それを伝えて買ってもらうという活動を、ブランディングデザインを使ってしっかりやっていく必要があると私は考えています。
実際に行われている方法
職人養成学校の設立
職人養成学校の設立は既に行わています。
また芸術や工芸の大学・専門学校でも伝統工芸に関する学科があるようです。伝統工芸に必要な技術も学べる可能性があります。
https://kaeru-kogei.com/learn-dentokogei-school
この記事の最初の方で総務省の資料を紹介した通り、国は既に伝統工芸の後継者不足を問題視しています。
だから調べれば職人養成学校はいくつも出てくるでしょう。
ただし職人を育成しても、伝える活動と売る活動をしなければいけません。日本人は職人気質ゆえに、ものづくりにはこだわりが強いですが、売る活動がおろそかになりがちです。
だから私としては職人養成学校にプロデュース科もあったらよさそうと考えています。
SPA
中川政七商店は伝統工芸の職人と提携してSPAを行っています。
https://www.nakagawa-masashichi.jp/shop/brand/masashichi
職人との提携があってこそ成り立つビジネスモデルです。
そして大手チェーン店が職人に仕事を提供することで、職人の収入も安定しますし、職人が作ったものの良さを多くの人に知ってもらうこともできます。
プロデュース
KEYUCAは全国各地の伝統工芸の職人が作った商品を扱っています。
https://www.keyuca.com/Page/user_data/areas_container.aspx
私も食器やお酒用のグラスをKEYUCAで揃えています。KEYUCAの伝統工芸品は優しい雰囲気のデザインで、お店で見ていても楽しいです。
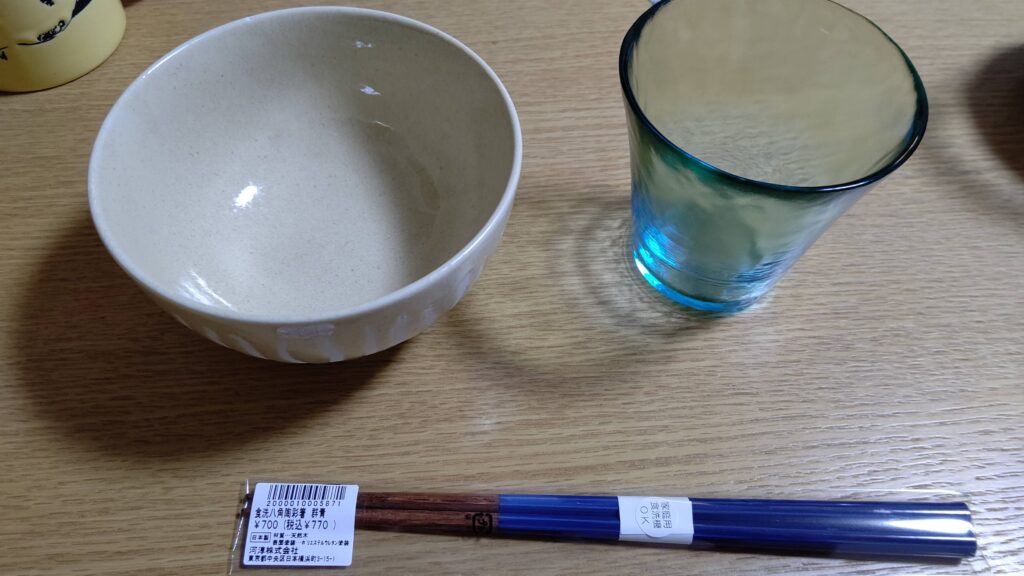
また最近はカルディで伝統工芸の器に入ったお菓子が期間限定で発売されていました。しかしパッケージを捨ててしまったし、ネット上にも情報がないので、どこの焼き物か解りません。

終わりに
私が伝統工芸の後継者不足について考えたり情報収集したりしたことを書いてきました。
やっぱり職人の技は凄く、私は伝統工芸品を気に入って使っています。だからこそ途絶えないようにしてほしいです。
しかしものづくりばかりでなく、プロデュースもしっかりとやっていかなければいけません。むしろプロデュースこそ重要と考えています。
あなたも作ることだけでなく、伝えることと売ることも考えて伝統工芸に取り組んでください。
