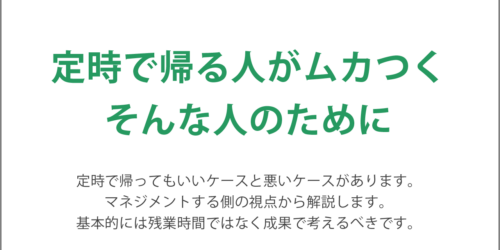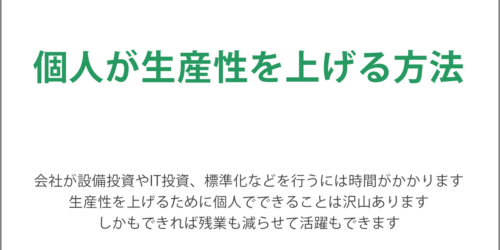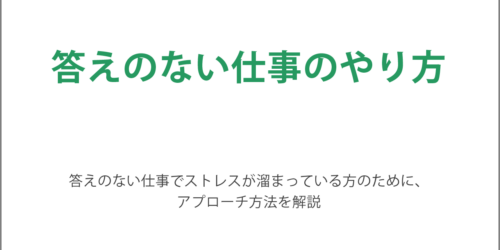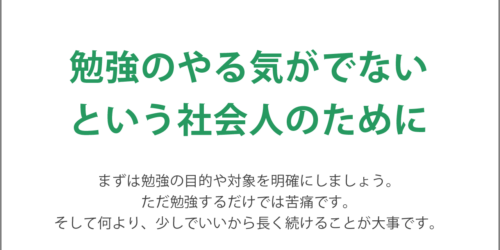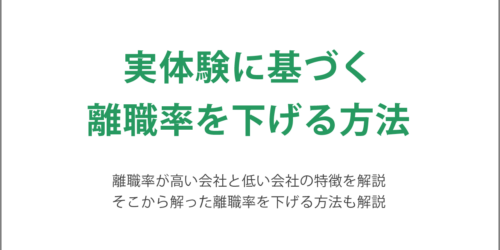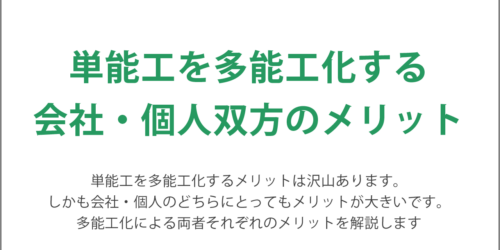成長するのに説教も残業も不要!ホワイト企業はぬるいという考えを改めよう
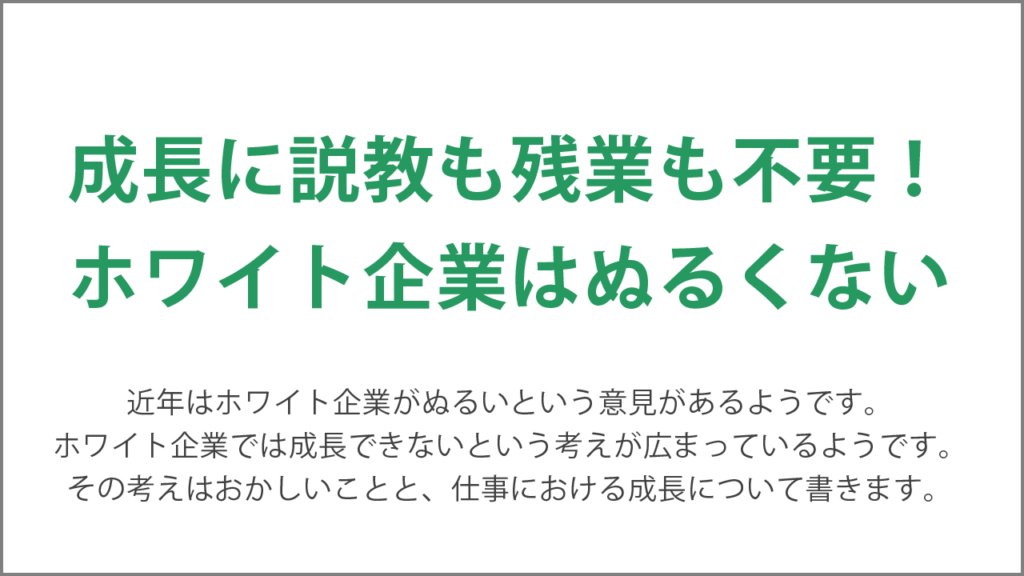
2020年頃から働き方改革によって残業を抑えて健全な働き方をしようという考えが広まりました。
また2010年代になって徐々に説教で人を管理するのではなく、人を上手く動機付けするというマネジメントが広まりました。
私はマネジメントを長年やっていて、マネジメントの論文を長年読み続けています。その立場からもこれは良い流れだと考えています。
ところが近年はこのような働き方を実践するホワイト企業がぬるいという意見があるようです。
そしてこのようなぬるいホワイト企業では成長できないという考えが若手の間でもベテランの間でも広まっているようです。
そこで今回はホワイト企業がぬるいという考えはおかしいことと、仕事における成長とは何かについて書きます。
ホワイト企業がぬるいと感じている方、ブラックな会社で経験を積もうと考えている方、成長を求める方、就職先で悩んでいる方などに参考にしていただければ幸いです。
ホワイト企業とは
ホワイト企業の定義
ホワイト企業の明確な定義はないようです。とはいえブラック企業と対照的な会社であるということは確かなようです。
簡単に言うと、残業が少なくてパワハラを中心とするハラスメントも少なく、説教も少ない会社です。そして働きやすくて安定した会社です。
ホワイト企業に勤めるメリット
ホワイト企業に勤めるメリットは大きいです。
まず給与水準が高いことが多いです。これは多くの労働者にとって大きなメリットでしょう。
また残業が少ないため、心身ともに負担が軽いですし、家庭や趣味の時間も確保しやすいです。自己研鑽の時間ももちろん取りやすいため、資格を取りたい人などにはメリットが大きいでしょう。
さらには有給休暇も取りやすいため、家庭や役所での手続き、旅行などもしやすいです。
パワハラを中心とするハラスメントも控えるような研修が行われているため、ストレスも少なくなります。
ハラスメントがあると嫌でも辞めざるを得なくなる可能性があるため、長く安心して勤められる環境だと言ってよいでしょう。
ホワイト企業がぬるいと言われる理由
冒頭でも書いた通り、私はホワイト企業がぬるいという意見に懐疑的です。そこでホワイト企業がぬるいと言われる理由を調べてみました。
残業や説教が少ない
ホワイト企業がぬるいと言われる理由として特に多いものが、残業や説教が少ないことのようです。
厳しく説教された方がしっかり意識して身に付けるから成長すると言いたいのでしょう。そして沢山残業した方がこなす仕事量が多いから成長できると言いたいのでしょう。
しかし人間は説教されるとモチベーションが落ちてしまいます。よって説教で成長などしません。説教はマネジメントができない管理職がやることであり、説教する管理職は能力がないと言ってよいです。
また残業は頑張っている証拠とされることが多いですが、とんでもない間違いです。
残業はマネジメントの失敗として発生します。仕事は沢山残業することが重要なのではなく、顧客に成果を納めることが重要なのです。
よって下手なマネジメントに耐えることが成長に必要という考えは根本的に間違っています。もちろん下手なマネジメントは反面教師としては優れています。
残業については私自身がマネジメントを長年やってきた経験から本当の話を書いています。是非読んでください。
無理なノルマやプレッシャーが少ない
ホワイト企業には無理なノルマやプレッシャーが少ないです。これが成長につながらないと言われるようです。
しかしこれも考え物です。
もし無理なノルマがあると、楽な方法で目標を達成することしか考えなくなります。すると新しい技術や方法論を試すことがなくなり、既にやり方が解っている技術や方法論しか使わなくなります。
よって無理なノルマがあると、進歩がなくなるのです。スラックと呼ばれる余裕リソース(時間や人手など)を持つことで、新しい技術や方法論を試すことができ、進歩ができます。
また企業の不祥事は過剰なノルマから発生します。ノルマを達成できないから黙ってサービス残業をして達成したり、会計的に不正なことをしたりするのです。
過剰なプレッシャーもまた考え物です。適度なプレッシャーはよいと私は考えますが、過剰なプレッシャーも無理なノルマ同様に問題につながる危険性があります。
安定しているので挑戦が少ない
ホワイト企業は安定しているので挑戦が少ないという意見があるようです。これには私も同意できます。
企業は立ち上げ当初こそ挑戦しないと潰れてしまう状態ですが、軌道に乗ってくると安定してきます。するといかに既存の顧客や製品を維持するかに注力するようになってきます。
こうなると安定志向が強まり、新たな挑戦すなわち新製品の開発や新規顧客の開拓などが減ってきます。
たしかに成長という観点からすると物足りないです。もちろん既存製品や既存顧客から既に出来上がったノウハウを学ぶことはできます。これは不安定な会社にはないメリットです。
成長に必要なこと
知識や技術を身に付けること
仕事における成長とは何でしょうか?
決して残業や説教や理不尽に対する耐性ではありません。中高年の中には仕事は厳しくて理不尽に耐えるものだという意見が多いため、このような意見も多くなります。
私も若い頃に何度もこのような話を説教されながら聞かされました。
しかしこれは間違いです。正しくは知識や技術を身に付け、出せる価値を上げることです。
仕事とは顧客の依頼に応えることであり、会社や上司の命令に従うことはその過程です。その会社や上司の命令がおかしいことが多いため、残業や説教や理不尽が横行します。
成長したければ残業や説教や理不尽に対する耐性を上げることよりも、知識や技術を身に付けることを重要視してください。
そしてもう1つ加えておきます。知識や技術がない人は根性論やKKD、残業に依存します。こうして残業と説教によるマネジメントが成立します。
逆に考えてみてください。残業300時間でも、毎日数時間も説教されても平気だけど、知識や技術はありませんという人が使えますか?下っ端作業者しかできませんよね。
仕組みを学ぶこと
仕事で成果を出すためには仕組みが重要になります。
業績がよい会社や仕事で成果を出している人は仕組み化が上手くできています。
一方で業績が悪い会社や仕事で成果を出せない人は、仕組み化が上手くできていません。それゆえ残業でカバーします。
自己研鑽すること
成長において知識や技術が大事である以上、自己研鑽はとても重要になります。
日頃から自分の仕事に必要な知識や技術を勉強するのです。これは自分のためにやることであり、自分で本を買ったり、実際にものを作ってみたりするのです。あるいは資格の勉強を自分でするのです。
もちろん会社に研修制度があれば活用してもよいです。会社に専門書があって、レンタルできるなら借りてきて読みましょう。
会社が福利厚生でeラーニングを契約してくれているなら、積極的に申し込んで活用しましょう。
会社に教えてもらうという受け身な姿勢では成長できません。自己研鑽はやった者勝ちですので、会社がどうこう関係なく積極的にやっていきましょう。
私も読書を習慣化していますし、マネジメントの論文を毎月読んでいます。更にはブログも書きますし、クリエイティブのトレーニングとして創作もやっています。
ホワイト企業を活用して成長する
研修制度を使う
ホワイト企業は研修制度が充実していることも多いです。なぜなら仕組みができているがゆえに効率良く稼げるため、研修制度を作る資金余力があるからです。
また従業員教育をしっかりやろうという意識も高いです。人を大切にするという名目(実際に大切にしているかどうかは別として)は大事にしています。
ホワイト企業ではない会社はOJTに頼ります。特にブラック企業などは根性論と場数で学べという考えをしています。
よってホワイト企業の研修制度をトコトン利用してやることは、成長のために有効であり、ホワイト企業ならではのやり方でもあります。
会社の仕組みを学ぶ
ホワイト企業は効率良く稼げる仕組みができているがゆえにホワイト企業たりえます。
仕事において個人の実力やチームワークは重要ですが、仕組みも重要です。
大企業の給与水準がなぜ中小企業より高いかというと、仕組みの差が大きいからです。大企業は仕組み化することで効率良く稼いでいます。
よってホワイト企業の仕組みをしっかりと学ぶことで、どういうやり方をすれば効率良く仕事を進められるのかを学べます。
自己研鑽を行う
ホワイト企業は残業が少ないです。また有給休暇も取りやすいです。ということはプライベートの時間を多く確保できます。
そこでプライベートの時間を使って自己研鑽を行います。
業務で必要な本や業界で流行していることに関する本を読んでみる、資格の勉強をする、自分で何か作ってみるなど、自己研鑽の方法はいくつかあります。
せっかく時間があるなら自己研鑽をした方が得です。もう会社が一生養ってくれる時代ではないため、いざというときは自己研鑽が自分を救ってくれます。
そして近年はYouTubeのような無料の教材も充実しています。詳細はこちらの記事に書いています。残業や説教に耐えるくらいなら、知識や技術を磨きましょう。
https://note.com/biginuneko/n/n65a508547a6c
例で考えてみる
ホワイト企業に勤める架空の人物とブラック寄りな会社に勤める架空の人物を使って、ホワイト企業に勤めることがぬるくもないことと成長につながることを解説します。
架空の会社と人物の例
大手ホワイト企業に勤めるAさん
Aさんはホワイト企業に勤めています。安定志向の会社で残業も少なく、有給休暇も取りやすいです。ミスをしても説教をされません。ただし既存事業の比率が高い会社です。典型的な安定大企業です。
中小ホワイト企業に勤めるBさん
Bさんもホワイト企業に勤めています。毎日定時で帰ることができ、有給休暇も好きに取れます。説教なんて絶対ないような会社です。
しかし高度な専門技術を持っており、ほとんどの仕事を元請けとして受注できています。会社の規模は中小企業です。ルールなんてなく自由奔放です。
ブラック寄りな会社に勤めるCさん
Cさんはブラック寄りな会社に勤めています。残業は多く、猛烈に働く人が多い会社です。そしてミスをすると厳しく説教されます。
ルールにも厳しい会社で、少しでもルールから外れると厳しく説教されます。また上司の命令も絶対です。
世間一般で言うとAさんやBさんの会社はぬるくて成長できないと言われています。そしてCさんの会社は厳しいけど成長できると言われています。
ホワイト企業とブラック寄りな会社の内情
それではこのような会社によくある内情を見ていきましょう。
Aさんの会社の内情
まずAさんの会社のような大手安定企業は、仕組みと知名度で稼いでいます。最近の働き方改革にも社会的責任として早めに取り組んでいます。典型的なホワイト企業です。
残念ながら新規事業や新製品を担当する機会は少ないため、挑戦の機会は少ないでしょう。一方で既存事業には多くのノウハウが溜まっているため、専門性を高めるにはよいでしょう。
やりたいことがあれば残業の少なさや有給休暇の取りやすさを活かしてやるのも手です。
Bさんの会社の内情
Bさんの会社は私が勤めてきた会社です。毎日定時で帰れて、有給休暇も自由に取れる中小企業です。しかし高度な専門性を持って元請けとして仕事をできるため、学びの機会がとても多いです。
その上毎日定時で帰れるため、自分が勉強したいことを勉強する時間も取れます。社内にはプライベートの時間で自己研鑽に励む人が沢山います。
Cさんの会社の内情
Cさんの会社は要注意です。残業も説教も多く、厳しく説教することで言うことを聞かせる会社は、マネジメントができない会社です。
言い換えると人を活かせない、人を育てられない会社です。
だから人材育成も根性論に依存した現場丸投げのOJTです。残業も多いため、なけなしのプライベートの時間を使って自分で勉強するしかありません。
また仕組みができていないがゆえに効率が悪く、仕事を上手く回せません。それを残業や説教で補おうとしています。
さらには知識や技術を軽視して、根性論やKKDを重視しています。だから単価も安くなり給与水準が低くなります。
また知識や技術がないがゆえに下請け仕事に甘んじ、安い単価で厳しい納期を押し付けられます。
このような会社では仕事を上手く回す方法や、知識や技術が身に付きません。そもそも会社がそのようなものをろくに持っていないからです。
このような会社は残業すればするほど偉い、頑張っているというありがちな論理で押し通します。また残業や説教を仕事とは厳しいものだからだとか、この仕事は厳しいのだと言って正当化します。
これを厳しいから成長できると考えてはいけません。知識や技術が身に付かず、仕事を上手く回す仕組みも学べないため、成長できないのです。
大事なものは残業や説教や理不尽への耐性ではなく知識や技術
もう一度言いますが、仕事において大事な要素は根性やKKD、残業や説教や理不尽への耐性ではありません。知識や技術です。
これは私が残業と説教ばかりで全然儲かってないブラック企業からホワイト企業に転職して実体験したことです。
ブラック企業が残業100時間以上する仕事をホワイト中小企業が毎日定時でやってのけるという実体験を私はしました。
そして他の多くの会社にできない高度な知識や技術を毎日定時帰りの会社が持っていたのです。むしろ高度な知識や技術があれば残業を減らしてホワイト企業になれます。
終わりに
世の中でホワイト企業がぬるくて成長できないと言われていることに疑問があったので、ホワイト企業もブラック企業も体験したことから私見を書きました。
どうも世間では仕事は厳しさが重要で、残業を沢山して説教を沢山され、理不尽な思いをしないと成長できないと考えられているようです。
仕事ができるとは価値を出せることであり、長時間の残業や説教に耐えられることではありません。そこを勘違いせず、知識や技術をしっかりと身に付け、顧客に対して価値を出せる人になりましょう。
関連記事としてキャリアやスキルアップに関することも書いています。こちらも是非読んでください。