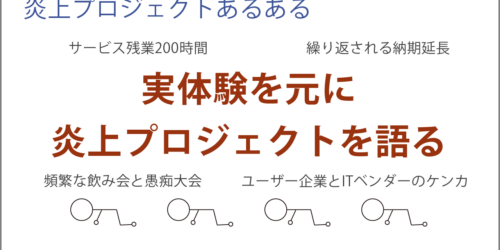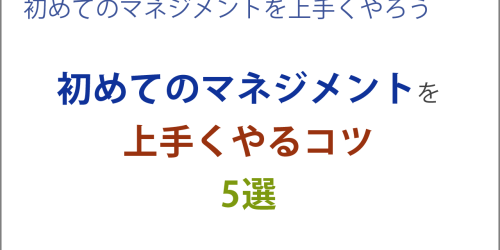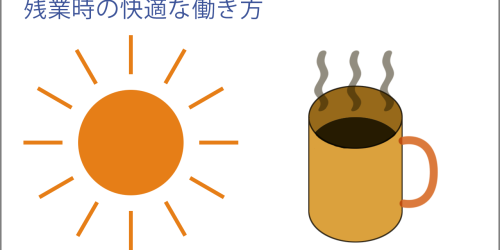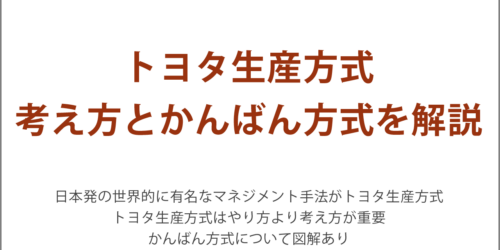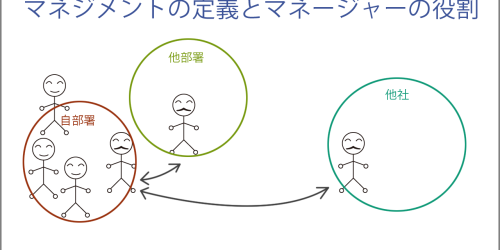認識違いで悩む方へ|仕事を上手く進めるコミュニケーション術を解説
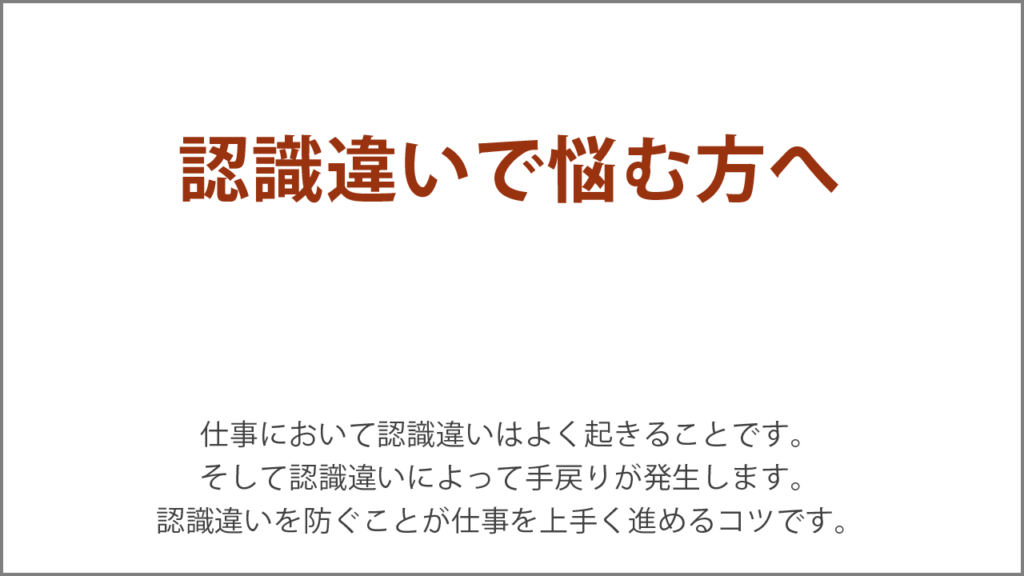
仕事において認識違いはよく起きることです。そして認識違いによって手戻りが発生します。
できるだけ認識違いを防ぐことが仕事を上手く進めるコツですが、それを上手くできる人ばかりではないです。
今回は仕事において認識違いで悩んでいる方、特に次のような方向けに、私が長年に渡ってマネジメントをやってきた経験を基に解説します。
- 経験が浅い方や新人
- せっかちでよく確認せずに進めてしまいがちな方
- 管理職やプロジェクトマネージャーになったばかりの方
- 営業や管理部門などコミュニケーションの機会が多い方
- 経験が浅い方向けの教育をしている方
認識違いについて
認識違いとは
認識違いとは思っていたイメージが話し手と聞き手とで合っていないことです。
例えば話し手は緑茶を買ってきて欲しいのに「お茶を買ってきて」と言い、聞き手はウーロン茶をよく飲むのでお茶と聞いてウーロン茶を買ってきたというケースが該当します。
この場合ですと、話し手が買ってきて欲しいものとは違うものを聞き手が買ってきています。思い込みや勘違いなどにより、正しく伝わっていないことが認識違いなのです。
このようなことは仕事でもプライベートでも日常茶飯事で起きます。
認識違いと言えばアンジャッシュのコントを見ると解りやすいです。
認識違いを利用してお笑いにしたのがアンジャッシュです。酷い認識違いを連発して、なぜか会話が成立しています。しかしお互いが全然違うことをイメージしています。
https://www.youtube.com/hashtag/アンジャッシュ
認識違いが起きる原因
認識違いが起きる理由は思い込みや習慣、勘違いなどです。
先ほどの例で言えば、お茶と聞いてイメージするものが普段よく飲むお茶である場合が多いため、人によって違ってしまうのです。
他にも相手が知らない言葉を使う場合や、言葉の定義が会社や業界によって違う場合に認識違いが起きます。
仕事においては、会社毎や業界毎の言葉の定義も確認した方がいいです。
聞く側の際に認識違いを防ぐコツ
ゴールや成果物を確認する
上司や先輩などから作業を指示された場合、ゴールや成果物を曖昧に言ってくることは多いです。
あなたも幾度となく経験しているでしょうけど、多くの人は相手が具体的にイメージできるように説明してくれません。ザックリと言ってきます。
本当は具体的に言わないといけないと私は考えていますが、人間はそこまで丁寧にできるものではないです。
よって作業を指示されたら、ゴールすなわち何が達成できればいいのかと、成果物の具体的なイメージを確認しましょう。
成果物の具体的なイメージとは、どんな情報が載っている資料ならいいのかとか、自社内でよく見かけるあの資料みたいなのでいいのかなどです。
どこでやるかを確認する
どこでやるかは意外と説明されないと感じています。話してもついつい言い忘れて認識違いを起こすものの代表です。
例えばどの店舗、どの設備、どのフロアでやるのか?などです。
システムの話になると、検証環境なのか本番環境なのかも重要な話です。
またどこでというにはちょっと変ですが、業務やルール、システムを新しくする話が出ている場合は、新と現行どちらの話なのかも確認した方がいいです。
その話は新業務、新ルール、新システムでやる話なのか、それとも現行業務、現行ルール、現行システムでやる話なのかをです。
これらは意外と省かれがちです。
私も顧客と話しているときに、検証環境か本番環境かを言わないせいで認識違いにつながったことがあります。
また新システムの話なのか現行システムの話なのか、Aシステムの話なのかBシステムの話なのかを言わないせいで、認識違いにつながり、こちらの言いたいことが伝わらなかったことがあります。
だから認識違いが発生していると感じたら、「どこで」について明確にしましょう。
優先度と期限を確認する
急ぎかどうかを察さないといけなくて、急いでやらなかったから怒られたというケースがあるかもしれません。
急ぎなら急ぎだと話す側が伝えるべきなのですが、それを端折ってしまう人も多いのが現実です。
そこで作業を指示された際には優先度と期限を確認した方がいいです。急ぎじゃないならまだしも、急ぎの作業だったら後で厄介なことになるからです。
具体的なイメージを話す
「今話している内容ってこういうことですよね」と具体的なイメージで確認しましょう。
具体的な作業手順や成果物のイメージでもいいですし、図で描いてもいいです。「例えるならこういうことですよね」でもいいです。
自分の言葉でイメージが合っているかどうかを確認しましょう。
話す側の際に認識違いを防ぐコツ
目的やゴール、背景を明確にする
相手に作業をしてほしいときは、目的やゴール、この作業を行う背景を明確に伝えましょう。
目的やゴールが明確でないと、イメージと違う成果物を提出されてしまいます。相手が理解できるまで具体化・詳細化をして伝えましょう。
ここではロジカルシンキングのテクニックが役立ちます。例えば詳細化するにはロジックツリーが有効ですし、やって欲しいことを漏れなく伝えるにはMECEが有効です。
また背景を話さないと相手にとって納得感がありません。やらされ仕事と化してしまうのです。
スケジュールを伝える
期限がある作業を他人に依頼するなら、スケジュールを伝えましょう。そうでないと後回しにされてしまいます。
期日だけだとそこまでのステップが解らないので、スケジュールを作りましょう。そしてどんな作業やステップがあるのかと、それぞれの予定日を明確にしましょう。
担当者を明確にする
他人に作業を依頼するときは担当者を明確にしましょう。
1対1で話しているときは特に意識しなくても問題にならないケースが多いです。しかし複数人を相手に話しているとき、例えば会議やスケジュール表などでは必ず担当者を明確にしましょう。
人は自分の担当なのかそうでないのかを気にします。自分の担当ならしっかりやらなければいけませんが、他人の担当なら勝手にやってしまうわけには行かないからです。
担当者が曖昧な作業は放置されます。必ず担当者を決めるようにしてください。
図表を活用する
文章や会話で中々伝わらないときは、図表を活用しましょう。
例えば構造や概念を表すときは図が有効です。図解の詳細について記事を書いていますので、是非読んでみてください。
漏れなく情報を整理したいときや、列挙する情報が多いときは、表を使いましょう。言葉で一々上げるのは面倒ですから。
認識違いを防ぐコミュニケーションのコツ
ここまで認識違いを防ぐための、聞く側と話す側の注意点を書いてきました。
しかし認識違いを防ぐコツはこれだけではないです。他にも沢山あり、特に私が気を付けていることをこちらの記事にも書いています。
終わりに
私もプロジェクトマネージャーとして顧客の様々な部署の人や、顧客と協業している様々なITベンダーの人たちと話してきました。その都度つまらない認識違いをしては謝ったものです。
そんな経験を今回は書きました。
認識違いで悩む方や、認識違いを減らすための従業員教育を担当する方などの参考になれば幸いです。