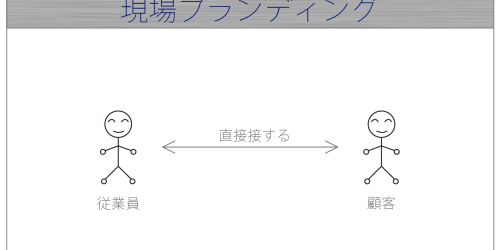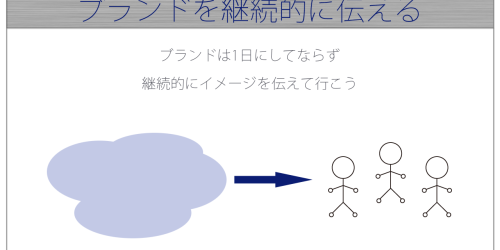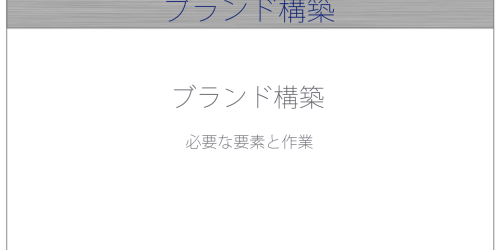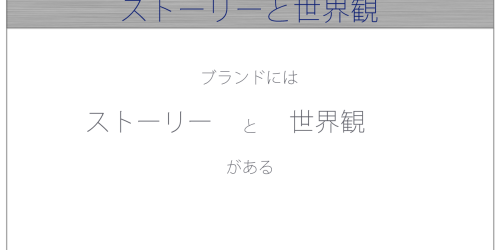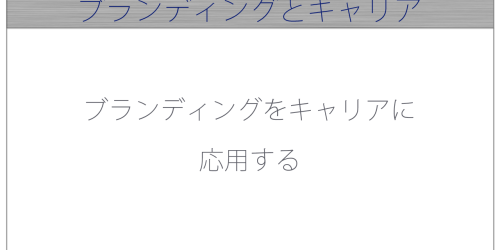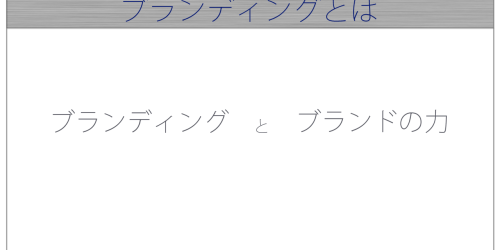ブランディングデザインはこれからの時代の経営にとって重要だ
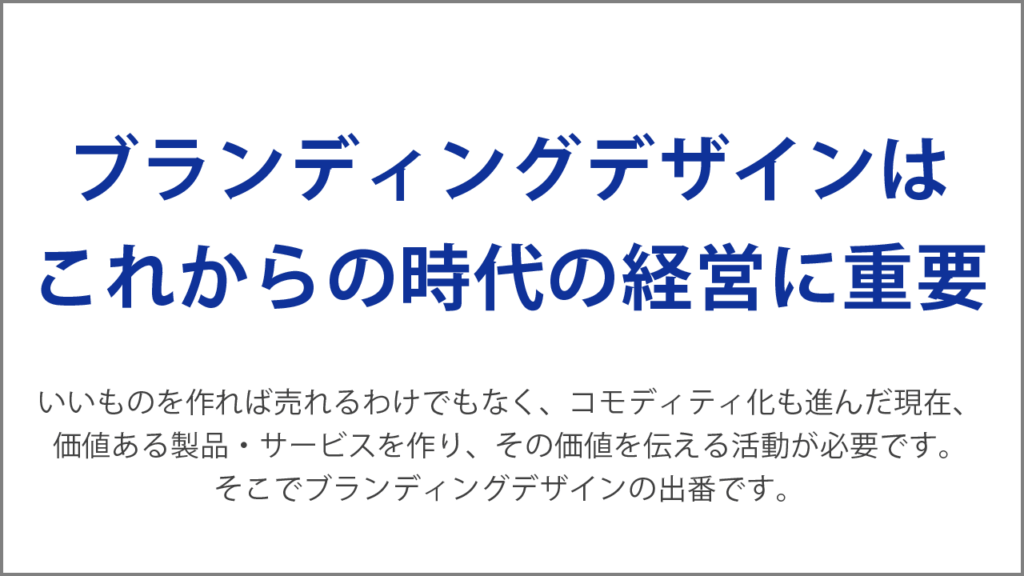
この記事ではブランディングデザインとは何かについてまとめるとともに、私がブランディングデザインがこれからの時代の企業経営にとって重要だと考える理由を書いてみます。
私は以前からブランドの価値に興味がありました。
なぜなら外資向けブランドを中心にシステムコンサルを行っている会社に勤めていたことがあり、また趣味でサイクリングをやっていて、自転車業界はブランドビジネスの世界だからです。
このようなことからブランドの力を信じており、そこに近年のデザイン雑誌で見かけるようになったブランディングデザインを組み合わせたら、とても強力だと考えるようになりました。
そこで今年はいよいよブランディングデザインの勉強に力を入れることにし、手始めに次の2冊の本を読みました。
特にエイトブランディングデザインの西澤氏が書いた「ブランディングデザインの教科書」は、実践しながら試行錯誤したことが感じられる内容で、とてもおススメです。
ブランディングやブランディングデザインに興味がある方、経営戦略で悩んでいる方の参考になれば幸いです。
ちなみに私はデザイナーでもブランディングコンサルでもないですが、マネジメントやITアーキテクチャーなどを仕事にしており、アマチュアクリエイターをやっています。
ブランディングとは
ブランドの語源
昔、酪農家が自分の牛と他人の牛を区別するために焼き印を付けたことがブランドの始まりだそうです。ちょっと意外なところにありますよね。
そこから他人の製品・サービスと自分の製品・サービスを区別するようになったのです。
ちなみにブランディングとは何かについてはこちらのブランディングマンというマンガがとても解りやすいです。
https://www.8brandingdesign.com/brandingman/all
マーケティングとの違い
ブランディングとマーケティングがごっちゃにされていると冒頭で紹介した書籍には書かれていました。私もそれは感じています。
マーケティングは宣伝や広告を駆使して製品・サービスをアピールしたり、ニーズやターゲット、競合との差別化を意識して製品・サービスを開発したりする活動です。
つまり売上につなげることがマーケティングの目的になります。よってマーケティングとは売るための活動です。
一方でブランディングは伝えるための活動です。このブランドはこういう特徴があるからいいものなんだよと伝えることが目的にあります。
ブランディングデザインとは
ブランディングデザインとはブランドをデザインすることです。
これだとザックリすぎるのでもう少し具体的に書きます。まずは広義のデザインと狭義のデザインから書きます。
世間一般で知られているデザインは、製品や広告のビジュアル面を作ることであり、これを狭義のデザインと呼びます。
広義のデザインは企画や計画、考案、情報の整理などを指します。これだと曖昧ですが、ビジネスをデザインすることに使います。
「ビジネス課題が〇〇だからであり、それゆえ××に取り組む必要がある。よってこういうデザインの製品・サービスを作る」というように、ビジネスの上流からデザインの考え方をしていくのです。
これがブランディングデザインで行う活動です。
広義のデザインという意味ではデザイン思考も同様です。製品・サービスや広告そのものではなく、仕組み作りから取り組んだりするのがデザイン思考です。詳細はこちらの記事を読んでください。
ブランディングデザインが重要な理由
ここからは私が世の中に対して感じていることや書籍で読んだことを基に、私がブランディングデザインが重要だと考える理由を書いていきます。
コモディティ化が進んでいるから
今の時代は製品・サービスの差別化が難しい時代です。コモディティ化はとても進んでいます。
現代は大量生産が可能なため、似たような製品を量産できるためです。
コモディティ化している以上は、競合と類似の製品・サービスが多くなります。そしてどこのブランドの製品・サービスを買っても同じということになってしまいます。
さらにコモディティ化すれば価格競争に陥ります。利益が下がり、大量生産や大量仕入れでコストダウンできる大手しか生き残れません。
だからこそブランドを作って磨くことによって価値を高めるのです。
イタリアに高級ブランドが多い理由は、国が小さいからこそ職人が作るものの価値を高める戦略を選んだためです。
もの余りの時代ゆえ価値が重要になるから
これもコモディティ化と似ています。
今はものが充足しています。となるとマーケティング論でよく言われる、いいものを作れば売れるわけじゃないということになります。
ものが沢山あるなら、どうやっていいものの価値を伝えていくかも考えなければいけません。価値を作り込み、価値を伝える活動を行うことで、この会社の製品がいいと顧客に思って買ってもらえます。
サービス業も類似のチェーン店が沢山ありますので、サービスもやはり製品同様に価値を作り込み、それを伝えていく活動が必要です。
多くの企業はバブル期をピークに売上が落ちているから
「ブランディングデザインの教科書」によると、多くの企業の売上がバブル期をピークに下がっていて、半分になっている企業も多いそうです。
私はこの話を読んでいて深刻だと感じました。それじゃ日本の給与水準は変らないし、むしろ無理して給料を払っているくらいじゃないかと。
だったらもっと製品・サービスの価値を高めて売上を上げないといけません。
日本には眠れるいいものが沢山あるから
私はマンガやアニメをあまりみないのですが、マンガのテーマは面白いと感じますし、アニメの技術はとてもきれいで素晴らしいと感じています。
マンガとアニメこそ日本が世界に誇れるコンテンツだと私は考えています。
また伝統工芸の美しさも素晴らしいです。日本人はクリエイティビティやデザインが苦手という話もありますが、伝統工芸の芸術性は格別です。
このような素晴らしいものがあるのだから、ブランド価値を高めて海外にもっともっと知ってもらった方がいいと考えています。
ブランディングデザインを実施する際の注意点
コンセプト作りなど上流工程をしっかりやる
いきなり製品やパッケージのデザインから始めてはいけません。トップダウンアプローチで取り組んでください。
まずは経営課題を明確にします。そしてそれに合ったブランドの戦略を考え、ブランドのコンセプトを固めていきます。
会社だってミッション・ビジョン・バリューやパーパスを定義します。そのような位置づけに当たるブランドのコンセプトを固めるのです。
本当はもっと考えることがありますが、詳細は冒頭で紹介した書籍を読んでください。
コンセプトに沿った製品・サービスを作る
コンセプトが決まれば、それを判断軸にできます。
単に流行だからとか売れそうだからという理由で製品・サービスを開発するのではなく、ブランドのコンセプトに合った製品・サービスを開発する必要があります。
そうしないとブランドは育ちませんし、イメージと大きく違えば顧客からは疑問を持たれます。
かつてユニクロが野菜事業に進出しましたが、違和感がありました。結局儲からなくて撤退しました。コンセプトに沿わないことをするとこうなるという事例です。
コンセプトやガイドに沿ってデザインする
コンセプトから外れないためにデザインガイドを作りましょう。ブランドイメージに合ったデザインをするために、フォントやレイアウト、色など細かいルールを作ります。
実はこれが重要なのです。
私は外資ブランドの仕事をしていたので知っていますが、グローバルブランドではグローバルでデザインを統一することが基本です。
それゆえ外資ブランドなどはVI(Visual Identity)と呼ばれるデザインガイドのルールがとても厳しいです。
私は外車のWebサイトを作ったことがあったのですが、ピクセル単位でレイアウトを指定され、使っていい色のカラーコードも明確に決められていました。
終わりに
今回はブランディングデザインについて、教科書で読んだこと、私自身が仕事で体験したこと、私が考えていることを書いてきました。
これからの時代にブランディングデザインはきっと役立つと、マネジメントを長年やっている者として私は信じています。
あなたも是非ブランディングデザインを活用してください。
最後に今回私が読んだ書籍を再掲します。「デザインを、経営のそばに」はデザイナーに発注する側の人向けで、とても解りやすかったです。是非読んでみてください。
「ブランディングデザインの教科書」はデザイナーやコンサル向けだと感じました。ブランディングデザインの実践ステップが濃く解説されています。