中小企業でもコストをかけずにてきる人材育成の方法を考えてみた
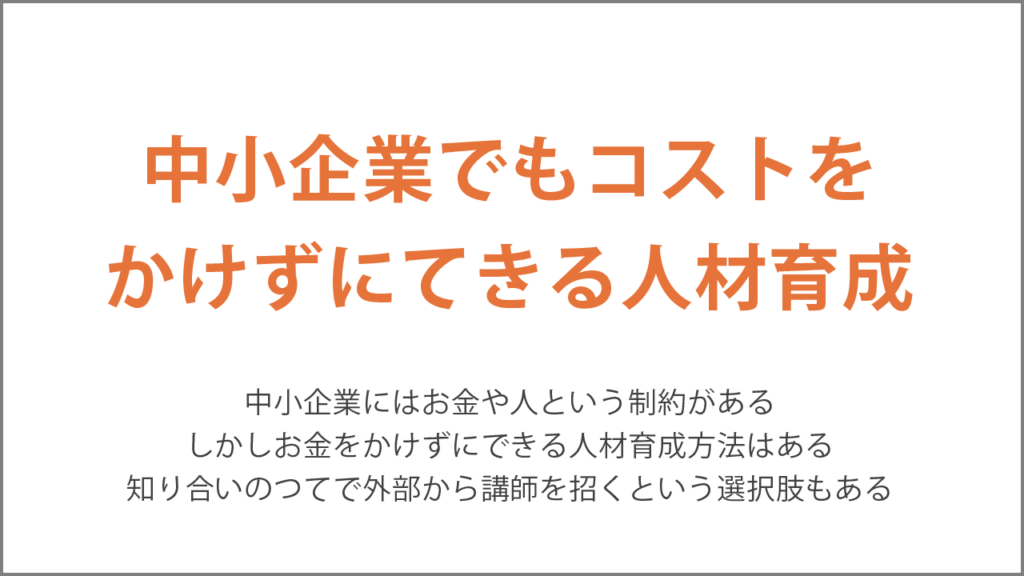
私は最近プロボノで中小企業の人材育成を考えています。そこで考えてみたことをまとめてみます。
当然ながら中小企業には人手やお金という制約があります。これらを考慮しています。
また私自身が転職経験が多く、人材育成に積極的な会社と消極的な会社を経験してきました。その体験から得たこともこの記事に盛り込んでいます。
中小企業で人材育成に悩んでいるという方の参考になれば幸いです。
人材育成の必要性
人材こそ企業の要
経営者がどんなに魅力的な事業を考えても、それを実行するのは人です。
経営者がどんなに素晴らしい製品やサービスを思い付いても、それを作って売るのは人です。
企業が活動を行うためには人が欠かせません。
もちろん会社を立ち上げたばかりなら経営者自ら作ったり売ったりするでしょう。
でもある程度会社が大きくなったら、経営者は考えることに専念し、従業員が実行する人になります。
だからこそ企業にとって人の質が欠かせません。そして人の質はピンキリです。
さらにはテクノロジーがどんなに進歩しても、使うのは人です。企業にとってどこまでも人は欠かせません。
人を育てることは投資と同義です。マネジメントにおいては特に重要なことです。その点についてこちらの記事に詳細を書いています。
伸びる会社は人を育てる
人は勝手には育ちません。1%くらいは自ら自己研鑽に励んでスキルアップする人もいるでしょう。でもそんな人はごくわずかです。
企業は人を育てなければいけません。会社は学校じゃないなんて単なる言い訳です。
私が何度も転職した経験から言うと、業績も従業員数も伸びる会社は人を育てています。
一方で人を育てず場数をこなせと言う会社は離職率が高く、売上も従業員数も横ばいでした。
人を育てることが結果的に業績向上につながるというフレームワークも存在します。それがサービスプロフィットチェーンです。人材育成の効果を知るためにも読んでみてください。
中小企業の人材育成における制約
教育コストの制約
人材育成は重要ですが、中小企業にはお金という制約があります。教育にかけられるお金が限られるのです。
よってあまりお金をかけずに人材育成を行う必要があります。
オーダーメイドの研修は高いので、社内勉強会やeラーニングを活用するなどを考える必要があります。
優秀な人材を集めづらい
中小企業は認知度や待遇が大企業に劣るため、優秀すなわち基本的な能力が高い人があまり応募してきません。
いわゆる高学歴や職歴が豪華な人はまず応募してきません。その人たちは待遇が良くて知名度もある大企業を選べるからです。
即戦力人材すなわち実務経験が十分ある人も、待遇を求めて大企業に応募します。
よって中小企業は学歴も職歴も並以下の人、あるいは学歴はあるけど職歴で失敗してる人などの中からポテンシャルのある人を探し、育てなければなりません。
人材育成の方針
キャリアパスを明確にする
人を育てるに当たり、まずはキャリアパスすなわちキャリアを積んで進んでいく道を明確にしましょう。
自社の事業に必要な職種や役割は何があるのか?これすらも解らずに事業を進めている会社は沢山あります。
それからよくある話ですが、マネジメントかエキスパートかという選択肢もあります。
さらにはスペシャリストかジェネラリストかという選択肢もあります。
マネジメントをやるならジェネラリストですし、エキスパートでも上流工程すなわち企画や要件定義などは知識の広さがものを言います。
下流工程は決まったことを粛々とやっていくことも多く、人数が多くて担当も分かれがちです。こういう工程では専門性の高さが物を言うので、スペシャリストが求められます。
このように職種や役割を明確にし、従業員個々人が自分の好みや適性に応じて選べるようにしましょう。
ロールモデルを明確にする
人間は目標があった方がモチベーションが上がるものです。
そこでロールモデルを用意します。こういう働き方、こういう役割で活躍している人がいるというものです。
残念ながら社内にロールモデルがいないかもしれません。その場合は経営者がコネの中から探すとか、プロボノを使うなどもありでしょう。
私もプロボノをやる側として、普段は他社に勤めている立場で支援していますので、こういう働き方も職種もあるという話をしたいと考えています。
経験資本を増やす
ハーバード・ビジネス・レビューにキャリアに関する論文が載っていました。
https://dhbr.diamond.jp/articles/-/11845
この論文では経験資本を増やすことが重要であると書かれていました。
たしかに実務経験さえ積めば、スキルも身に付きますし、即戦力とみなされやすく、仕事を選べる立場になります。
そして経験資本を積むためには、必要なスキルのうち新しいスキルの比率が25%くらいになるような仕事に配属するといいそうです。
他にはリーダーシップや損益責任を体験させるといいそうです。
私もマネジメントを長年やってみて、自分で決めるという立場で学べることは多いと感じています。
偶発的計画性を利用する
偶発的計画性とはキャリアのほとんどは偶然によるものだという理論です。具体的にどういうことかはこちらの記事を参照してください。
https://diamond.jp/articles/-/339423
書籍も出ていますので、気になる方は読んでみてください。
偶発的計画性を人材育成に利用したらいいんじゃないかと私は考えています。
つまりたまたまこういうことを知っている人に会った、たまたまこういうことを教えてくれる人がいたというものです。
社内にそんな上司や先輩がいればいいですが、そうとも限らないでしょう。そこでプロボノとか経営者のコネで、社外から講師を呼ぶのです。
そうして社内だけ見ていたらそんな知識を得ることはなかった、そんな職種や役割があるとは知らなかったと従業員に感じてもらうのです。
コストをかけない人材育成の具体的な方法
実技と座学を組み合わせる
実践は大事ですが、視野を広げ視座を上げるためには座学も必要です。
実践と座学を組み合わせていきましょう。
有識者を講師とした勉強会を開く
知識の共有は手っ取り早くローコストですが有効です。
経験が豊富な従業員のノウハウを社内勉強会で共有しましょう。
資格取得を推進する
資格の勉強をすることで、その資格が対象とする仕事に必要な知識を広く得ることができます。
また研修会社に研修を頼むのと比べると、資格の取得手当を払う方がローコストです。
よって資格の取得を推進することも従業員を育てるのに有効です。
低価格なeラーニングを導入する
最近は低価格なeラーニングサービスがたくさんあります。Schooなどが代表的な例です。
e ラーニングは自分のペースで勉強することができ、手軽に知的好奇心を満たすことができます。
ただし仕事が忙しくなるとサボりがちになるのが難点です。
ライトニングトーク会を実施する
ライトニングトークとは5分から15分程度の短時間のプレゼンテーションです。
ライトニングトークをやることで、書くことと書くこと話すことを練習できます。
勉強したいことあるいは仕事で学んだことをテーマにプレゼンテーションすれば、ライトニングトークをやるたびに1つ学びを得ることができます。
外部から講師を招く
3〜5万円程度の謝礼が必要になりますが、外部から講師を招けば、自社の従業員とは違う視点から語ってもらいつつ有識者から学べます。
外部の講師の話を聞けば、普段はあまり聞けない話も聞けて、いい刺激にもなります。
大事なことは継続すること
まずは試行錯誤する
いきなり上手くいくことはよほどラッキーでなければありません。
まずは実験と思って取り組みましょう。
また知人の会社に同じような取り組みをやっていないか聞いてみるのも手でしょう。
上手く行き出したら続ける
何事も継続が大事です。上手く行き出したら続けましょう。
ただし負担が特定の従業員に偏らないように持ち回り制にしましょう。
終わりに
今回は私が何度も転職して、人を育てられている会社とそうでない会社を実体験したことから、人材育成について考えてみました。
いずれもプロボノで実践するために中小企業でもできるローコストな方法になっています。
正解はないので思いついたこと。試してみつつ上手いやり方を探っていきたいと思います。



